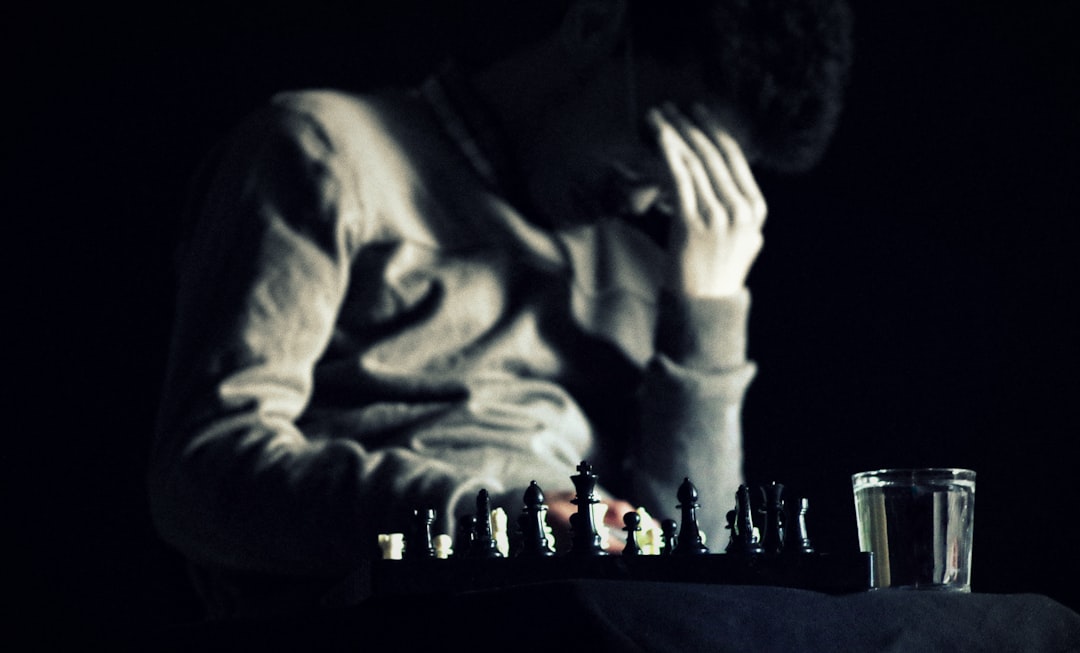日曜日が休みの会社員の中には、夕方になると気持ちが沈み始める人が少なくないはずです。それは「サザエさん症候群」にかかっている表れかもしれません。しかし、サザエさん症候群の名前を知っていても、原因や対策がわからない人もいます。そこで今回は、サザエさん症候群について診断方法も交えながら解説します。
監修者

キャリアアドバイザー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
サザエさん症候群とは
サザエさん症候群はうつ病と違い、正式な病名ではありません。しかし悪化すると、仕事やプライベートに悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、サザエさん症候群について詳述します。
サザエさん症候群の意味
サザエさん症候群とは、日曜日のたびに翌日の月曜日からのことを考えて憂鬱な気持ちになったり、体調が悪くなる状態を意味します。気分が沈み始めるのは、日曜日の夕方から深夜にかけてが多いようです。
平日が休みの人でも、翌日から仕事が始まると考えると似たような状態になる場合は、サザエさん症候群だといえます。
サザエさん症候群の由来
サザエさん症候群の由来は、毎週日曜日の18時30分から放映されている「サザエさん」によります。サザエさんは言わずと知れた日本の国民的アニメで、1969年から放映を開始して以来50年以上、ほとんど放送中止や延期にならずに現在に至ります。
そのためサザエさんを観ると、「もう休みが終わる」と感じる人が大半です。それが引き金になって、「明日の月曜日からはまた仕事だ」という感情を呼び起こされてしまうことで、憂鬱な気分や体調不良につながっていくことから、サザエさん症候群と呼ばれるようになりました。
海外のサザエさん症候群
海外でも日曜日になると、サザエさん症候群と同様の症状が表れる人がたくさんいます。その名称は、以下の通りです。
- Blue Monday Syndrome(ブルーマンデー症候群)
- Monday Blues
- unday Night Blues
- Monday Morning syndrome(マンデーモーニング症候群)
- 月曜病
これらの病名からは、何が憂鬱な気分や体調不良を誘発するのかはわかりませんが、翌日から仕事だと思うと気持ちが沈むのは万国共通なのかもしれません。
サザエさん症候群になる人は多い
サザエさん症候群になるのは、決して特別なことではありません。どんなに優秀な会社員であってもミスやトラブルによって仕事に行きたくなくなることはありますし、過労や劣悪な労働環境で働く人にとって、月曜日を迎えたくない気持ちを持つのは当然のことです。
日曜日になると、Twitter上にサザエさん症候群に苦しむ人の声がたくさんアップされます。
先月部署変わってからサザエさん症候群がぱねぇ。働きたくない😇会社行きたくない😇
— ❤︎ちっぴぃ❤︎D垢(共通)❤︎TA (@TA10010516) May 12, 2019
やるべきことを何もしてないまま連休が終わる…。サザエさん症候群しんどい。
部屋の汚さだけでもなんとかしたかった…。— 桜@もす。 (@DABADG5) May 6, 2015
社内での異動や日々の激務によって、休日に活動しようという気力をなくす人もいます。日曜日の夕方になるとサザエさん症候群で気分がふさいだり、体調が悪化することで苦しむ人が多いことが、このコメントから読み取れます。
サザエさん症候群の症状・診断方法
サザエさん症候群かどうかを見分けるためには症状を知っておくことが大切です。日曜日の夕方以降に表れる、サザエさん症候群の主な症状は以下の通りです。
以下の項目を1つずつみることに時間をとって、自分が何個当てはまるかを診断してみましょう。
- 憂鬱な気持ちになる
- 涙が出てくる
- 頭痛がする
- 胃痛がする
- 吐き気がする
- 身体がだるくなる
- 発熱する
- 翌日のことが気になって眠れなくなる
診断の目安として、上記の症状が複数表れている場合は、サザエさん症候群の可能性が高いです。放置するとうつ病に移行する可能性がありますので、軽視してはいけません。
また、上記項目のほとんどが当てはまる人は重症であると、診断結果を重く受け止めるべきです。無自覚のうちに更なる重症化を防ぐためにも信頼できる人への相談、精神科医の診察を受けるなど即行動を取りましょう。
以下の2つの記事では、仕事に行こうとすると吐き気を感じる、あるいは朝になると体調が崩れる原因と対処法について解説しています。誰にでも起こりうることなので、ぜひ一読してみてください。
サザエさん症候群になりやすい人の特徴
サザエさん症候群に苦しんでいる人を見ると、共通する特徴があるようです。具体例として、以下のことがあげられます。
- 慢性的な睡眠不足である
- もともと感情の起伏が激しい
- 休日に寝だめしようとする
- 趣味がない
- 休日は自宅で1人で過ごすことが多い
休日に生活リズムを崩したり、ストレス解消につながる趣味や孤独を感じない時間を過ごせないでいると、サザエさん症候群を発症しやすくなると考えられます。
サザエさん症候群の原因
サザエさん症候群は、誰にでも起こりえます。しかし、圧倒的に働く会社員が発症するケースが多いようです。ここでは、サザエさん症候群の原因について説明します。
サザエさん症候群の主な原因は仕事のストレス
サザエさん症候群の主な原因は、仕事のストレスです。仕事をしていると、業務に対する不満や長時間労働、職場の人間関係など、様々なストレスにさらされるのが一般的です。
休日はそこから距離をとることができますが、翌日から仕事だと思うと改善できないストレスを思い浮かべ気が重くなるのは、サザエさん症候群でなくてもあることです。
ストレスを引き起こす4つの要因
仕事のストレスといっても多岐にわたります。しかし、会社や仕事内容以外にも、ストレスの要因はあります。ここではストレスを誘発する、4つの要因について詳述します。
①生活習慣が乱れている
休日になると寝坊や昼寝をしたり、食事時間がバラバラになるなど、生活習慣が乱れることがストレスを引き起こしている人が少なくありません。
人間は生活リズムが崩れていると、活動の際に余計なエネルギーを使います。日曜日に寝坊した結果、夜に寝付けなくて月曜日を寝不足な状態で迎えると、心身ともにネガティブな状況に陥ります。
②休日が充実していない
趣味や外出の予定もなく、休日を漫然と自宅で過ごしている人も多いことでしょう。しかし、趣味や友人との会話などに時間を費やしたり、スポーツをして肉体的な疲労を感じることが、人間をポジティブ思考にすることにつながっています。
休日に特に予定がない、やりたいことがないという充実したとはいえない時間を過ごしたまま日曜日の夕方を迎えると、よりネガティブ思考になってしまいがちです。
③仕事が苦痛
担当している業務に苦手意識がある、作業自体が苦痛であると感じていると、生活リズムを整えていてもサザエさん症候群を発症することがあります。やりたくないことを無理に続けていることで、心が悲鳴を上げている状態といえるかもしれません。
その場合は、異動や転職を含めて、苦痛に感じない仕事の就くことを検討するのも選択肢の一つです。
④仕事や私生活で満足感を得ていない
仕事で多少のストレスがあっても、私生活が充実していれば乗り切れるという人は珍しくありません。しかし仕事でも私生活でも満足感を得られていないと、気持ちが沈んでしまいます。
例え仕事でそれほど大きなストレスを抱えていなくても、自分の生活の中で満足感や充実感が得られなければ、日々がつまらなく感じてしまい、サザエさん症候群につながっていくことがあります。
サザエさん症候群の対策・克服法
サザエさん症候群を改善するためには、その原因を取り除くのが一番です。また、対処法を日々実践することで、サザエさん症候群を予防することにもつながります。
ここでは、サザエさん症候群の対策・克服法について説明します。
休日を有意義に過ごす
サザエさん症候群を克服するためには、休日の過ごし方を改善するのがおすすめです。ここでは、休日を有意義に過ごす方法を4つ、紹介します。
有意義に過ごす方法①|日曜日だからといって寝すぎない
まず、日曜日だからといって寝坊しないことです。気分の落ち込みを避けるためには、休日であっても平日と同じ生活リズムを守ることが大事です。
そして、朝起きたらきちんと日光を浴びましょう。幸せホルモンと呼ばれることがある「セロトニン」は、日光を浴びることで分泌されます。セロトニンは精神を安定させてくれるので、毎日の週間にしましょう。また近年、休日に寝だめすることで生活習慣病・不眠・抑うつ症状が発症するリスクが高まるという研究結果が出たようです。十分に注意しましょう。
有意義に過ごす方法②|昼間に出かける予定を入れる
朝寝をし過ぎないためにも、日曜日の昼間には出かける予定を入れましょう。その目的は、人それぞれです。
- 友人と会っておしゃべりに花を咲かせる
- デートする
- カラオケに行く
- スポーツジムに行く
- 映画を観る
- セミナーやイベントに参加する
- 美術鑑賞
- 散歩する
こうした自分の楽しみにつながる行動は「アクティブレスト(積極的休養)」と言われ、身体を動かすことで決州の改善や疲労物質の排出を促すだけでなく、精神的なリフレッシュにもつながります。
有意義に過ごす方法③|夜に少しだけ仕事や勉強に取り掛かる
日曜日の夜に、少しだけ仕事をするのも対策方法の一つです。月曜日の朝からいきなり仕事モードに入るより、前日に心の準備をしておく方が心理的な負担が少なく済むからです。
翌日の予定を確認したり、メールチェックをする程度でかまいませんので、ぜひ実践してみてください。
有意義に過ごす方法④|月曜の夜に楽しみな予定を立てる
憂鬱な月曜日だからこそ、その日の夜に自分が楽しめる予定を入れることもおすすめです。その日のお楽しみがあれば、「退勤までがんばろう!」という気持ちが持てます。
予定は友人や恋人との食事でも、レンタルしたDVDを観ることでも、エステやマッサージでも構いません。月曜日1日を乗り切れるお楽しみを、自分なりに探してみてください。
ストレスの原因を知りストレス発散をする
サザエさん症候群を改善するためには、自分のストレスの原因を知り、発散させることも大事です。ここでは、主なストレス発散法について紹介します。
ストレス発散方法①|軽い運動をする
生活習慣を整える方法として、軽い運動を習慣化することをおすすめします。疲労を回復させるためには、ある程度身体を動かすことが大切だからです。そして軽い運動は、精神的な疲労を回復させることにもつながります。
毎日運動するのは難しくても、3日に1回筋トレやストレッチをする、休日にウォーキングやジョギングをすることはできるはずです。YouTubeには、自宅で15分程度でできるダンスエクササイズなどの動画がたくさんあがっていますので、できるものを取り入れてみましょう。
ストレス発散方法②|何か集中できることに取り組む
ストレスを解消するには、仕事を忘れて没頭できる時間が必要です。そこで日曜日には、何か集中できることに取り組みましょう。趣味がある人は、休日はそれを楽しむ日と決めるのもおすすめです。
もし趣味がないと感じているなら、掃除や洗濯、アイロンがけ、料理といった家事に没頭するのもおすすめです。フローリングのワックス掛けなどは重労働ですし、終わった後に達成感を味わえます。もちろん、筋トレやジョギングなど運動に集中するのも方法の一つです。
ストレス発散方法③|規則正しい生活を心掛ける
日曜日であっても、起床・睡眠・食事の時間は平日と同じになるように意識すれば、生活リズムが崩れにくくなります。サザエさん症候群を避ける意味でも、規則正しい生活を心掛けましょう。
そのためには、自分に適した睡眠時間を知ることが大事です。平日・休日問わず、自分がスッキリと目覚められた時の睡眠時間をチェックして、それを確保するよう意識すると、疲労が残りにくくなるはずです。
ストレス発散方法④|仕事が苦痛なら対策をとる
サザエさん症候群に苦しむ人の中には、仕事自体が苦痛な人も少なくありません。その場合は、生活習慣や休日の過ごし方を改善しただけでは、症状が軽減されない可能性が高いです。もし仕事や職場が苦痛で仕方がないなら、異動や転職を検討するのもおすすめです。
仕事がつらいと思う自分が悪いと思い込んでいる人もいますが、その原因が他にあるケースも少なくありません。以下の記事では、仕事がつらいのは甘えではないと言い切れる根拠や事例について説明しています。ぜひ参考にしてみてください。
オンとオフの区別をしすぎない
平日は仕事、休日はプライベートと明確にしていると、積極的にやりたいこととそうでないことに分かれてしまいます。その結果、仕事をやりたくないという気持ちが大きくなるのです。
そのためにも、オンとオフの区別をしすぎないことを意識してみましょう。前述したように、休日の夜に少しだけ仕事をして翌日に備えると、気持ちが無理なく仕事モードに変わるのでおすすめです。また、平日に趣味の時間をつくって、気分転換をはかるのもよいでしょう。
サザエさん症候群はうつ病とは違う
サザエさん症候群は正式な病名ではなく、うつ病とは違います。非定期型うつ病と似ていることから、混同されることもあるようです。
サザエさん症候群とうつ病は、発症期間や症状の持続力、治療方法の有無など、様々な違いがあります。その違いを以下の表にまとめてみました。
症状が長期化、重症化し、曜日に関係ない時にはうつ病が疑われます。
サザエさん症候群が重症化した場合
サザエさん症候群び症状が休日だけでなく、憂鬱な気持ちや体調不良が常態化している場合は、うつ病に移行した可能性があります。うつ病を発症した可能性がある場合は、専門医による治療が必要です。ここでは、サザエさん症候群が重症化した場合にとるべき手段について説明します。
病院にかかる
うつ病を発症した可能性がある場合は、まず専門医に診断してもらうことが先決です。心療内科や精神科を持つ病院を、受診することをおすすめします。 症状が軽度であれば投薬やカウンセリングを続けながら仕事を継続できますが、重症化すると休職を勧められることもあります。
まず病院で診察を受け、自分の状態を把握することから始めましょう。そして、適切な治療を受けてください。
相談機関を利用する
サザエさん症候群が重症化していると感じた時には、相談機関を利用するのも選択肢の一つです。会社の産業医やメンタルヘルス関連の部署に相談する他、インターネットでも相談を受け付けているサイトがあります。
また厚生労働省でも「心の耳」というサイトを運営しており、専門相談機関を紹介してもらうことができます。以下の記事では年代別の仕事の悩みだけでなく、心の耳の紹介もしています。ぜひ一読してみてください。
転職・退職も視野に入れる
ストレスの大元が職場環境や仕事内容だった場合には、自分の力だけでサザエさん症候群の重症化を止めることはできません。うつ病を発症する前に、転職や退職を検討することをおすすめします。
退職代行サービスを利用することもおすすめです。
自分のやりたいことや、仕事におけるプライオリティが明確であれば、きっとイキイキ働ける職場が見つかるはずです。
まとめ
今回は、サザエさん症候群について解説しました。
休日の夜に憂鬱になるという経験は、誰でも一度くらいしたことがあるでしょう。また、放置して重症化するとうつ病を発症するリスクもあります。原因や対処法を知ることで、サザエさん症候群を改善する行動につなげてください。