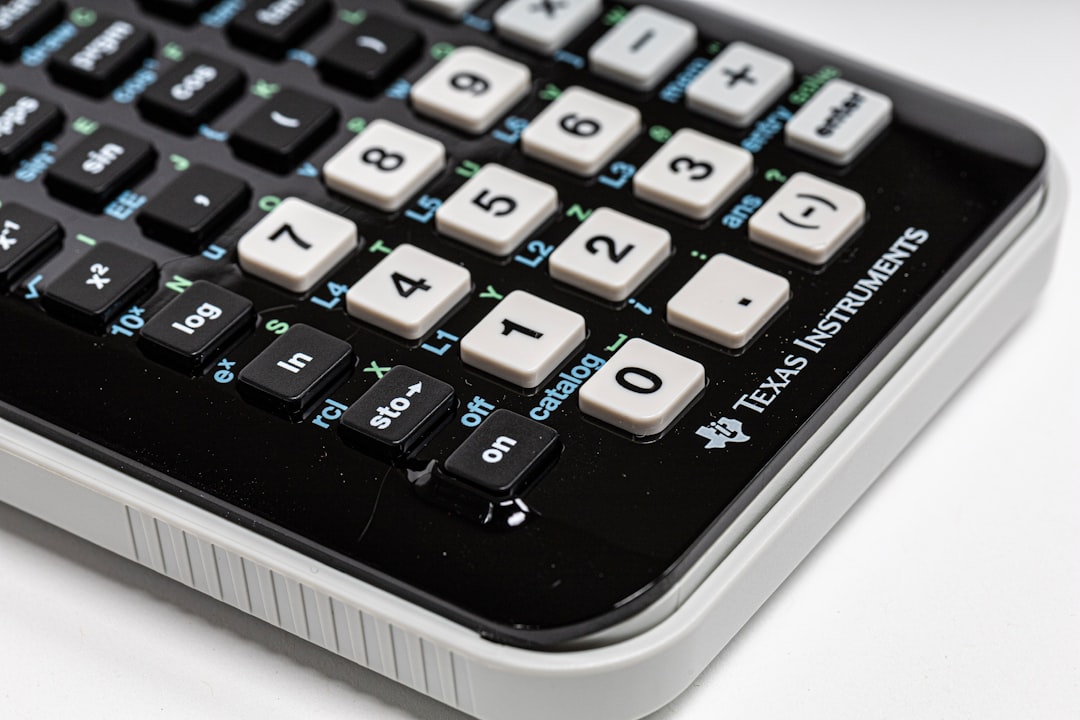就職先を決める際、給与に加えて扶養手当は重要な判断基準となります。特に、公務員は基本給が低いため、扶養手当の有無は長期的な人生設計においても不可欠だと考えられます。本記事では、まず公務員では扶養手当があること、扶養手当の受け取り方について。次に、扶養手当と扶養控除の関係や今後の傾向を解説致します。
監修者

キャリアアドバイザー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
公務員にも扶養手当はあるか
民間企業では、扶養手当を支払う企業がありますが、公務員にも扶養手当はあるのか知りたい方がいらっしゃると考えられます。
本見出しでは、公務員にも扶養手当があるかという疑問に対する回答と、その解説を致します。
公務員の扶養手当は法律で厳密に決まっている
結論として、公務員の扶養手当は法律で厳密に決まっており、民間企業と同様に扶養手当が支払われています。
- 第11条1項: 扶養手当の支給について
- 第11条2項: 扶養家族の対象規定
- 第11条3項: 扶養手当の月額
上述のように、一般職の職員の給与に関する法律では、扶養親族のある公務員に対して、扶養手当を支払っています。
公務員は、国民の税金により給与が支払われているため、不正受給などがないようこのように法律で扶養手当を定めていると考えられます。
公務員が扶養手当を受け取るには
前述の見出しにて、公務員も扶養手当を受け取れることが法律で規定されているとわかりましたが、どのようにして受け取るのでしょうか。
こちらの見出しでは、公務員が扶養手当を受け取る条件と、扶養手当を受け取れないケースをそれぞれ解説致します。
扶養手当を受け取る条件
扶養手当を受け取る条件として、人事院では対象となる扶養家族の規定を行なっています。
- 配偶者: 事実上婚姻関係にある者を含む
- 子: 満22歳となった最初の年の3月31日まで
- 孫: 満22歳となった最初の年の3月31日まで
- 父母: 満60歳以上であること
- 祖父母: 満60歳以上であること
このように、扶養手当を受け取れる条件は、申請者である公務員からみた立場によって細かく定められています。
そのため、この条件を満たさなくなった場合は、速やかに扶養手当の受給を止めなければなりません。
扶養手当を受け取れないケース
扶養手当を受け取れないケースとしては、以下が例として挙げられます。
- 上述の扶養条件を満たさなくなった場合
- 組合員が主たる扶養者でない場合
- 扶養者以外から手当を受け取っている場合
- 年間130万円以上の収入がある場合
仮に、扶養手当を受給した後で条件を満たしていなかったと判明した場合、扶養手当の不正受給として返金が求められることになります。
扶養手当の申請にあたっては、その条件を満たしているか否かに加えて、条件外となった際の対応もあわせて把握してことが推奨されます。
育休と扶養手当の関係
扶養手当の対象として、配偶者がありましたが出産や育休時には、扶養手当が支払われるのか疑問に感じた方もいらっしゃるかもしれません。
そこでこちらの見出しでは、民間企業に勤める夫と公務員の妻を例として、育休と扶養手当の関係を解説致します。
夫が会社員、妻が公務員の場合
夫が会社員で、妻が公務員の場合、夫の被扶養家族に妻を入れられるかがポイントとなります。
- 妻が育休で無休の場合
- 妻が育児休業給付金を受け取っている場合
民間企業では、扶養家族の規定が法律ではなく会社の規則によって定められているため、一概に育休中の妻を被扶養家族にできるとは限りません。
例えば、上述の通り同じ公務員でも、育休中の経済状況が異なるため、勤め先である民間企業の人事に確認をすることが必要となります。
扶養控除との違い
扶養手当と似たような言葉で、扶養控除がありますが、どのような意味なのか知らない方も多いと考えられます。
この見出しでは、扶養手当と混乱しやすい扶養控除とは何かを解説致します。
扶養控除は所得から引かれる金額
扶養控除とは、納税者本人に配偶者以外の扶養家族がいる場合、扶養家族の人数に応じて所得金額から控除をして、税負担を減らす制度です。
- 配偶者以外の親族
- 養育を委託された養児
- 養護を委託された老人
- 納税者と生計を1つにしている
- 年間の合計所得金額が38万円以下である
- 青色/白色申告者の事業専従者でないこと
扶養家族の対象範囲としては、これらの要件を満たしていることが挙げられます。
また、扶養控除額は扶養家族の区分によって、以上のように金額が分かれています。
公務員が受け取れる手当
扶養控除と扶養手当の違いをご理解頂けたと思いますが、扶養手当以外ではどのような手当があるのか気になるかもしれません。
そこでこちらの見出しでは、公務員が受け取れる手当をご紹介致します。
以下が、扶養手当の他に公務員が受け取れる手当となっており、給付されるかは各国家機関や地方自治体によって異なっています。
- 住宅手当
- 清掃作業手当
- 税務手当
- 用務交渉手当
- 独身手当
公務員は、一般的に民間企業よりも基本給が低く定められており、業務内容も担当部署や課によって異なることが特徴となります。
そのため、これらのような手当を給付することで、業務負担の不均衡を緩和することを目指しています。
今後、公務員の扶養手当はどうなるか
ここまで、公務員の扶養手当に関して解説をして参りましたが、今後も公務員であれば条件に応じて扶養手当を受け取れるのでしょうか。
この見出しでは、本記事の締めくくりとして「今後、公務員の扶養手当はどうなるのか」について、傾向を解説致します。
扶養手当は減額される恐れがある
結論として、公務員の扶養手当は減額される恐れがあると考えられます。
- 公務員も基本給の給与が上がっている
- 人口減少で税収入が減っている
- 働き方が変わり共働き世帯が増加している
以上が、公務員の扶養手当が減額される理由として考えられますが、具体的な減額開始時期や減額の割合はこれから決まっていく見込みです。
公務員の家族がいて扶養手当を現在受け取っている場合には、家計の収支バランスを見直すなど抜本的な対策が必要だと考えられます。
まとめ
本見出しでは、公務員も扶養手当を受け取ることができますが、その条件は法律で定められており、扶養控除とは違う意味だとわかりました。
また、扶養手当以外にも公務員は様々な手当を受け取っていますが、今後は減額の恐れもあるため収支の見直しなどが必要だと考えられます。