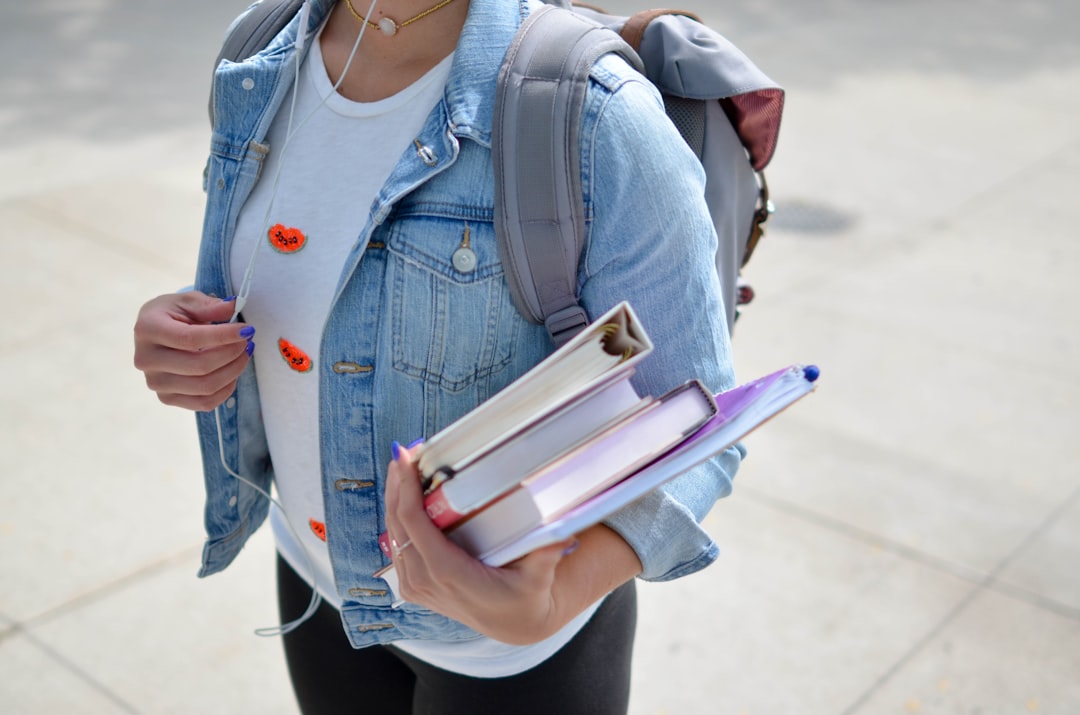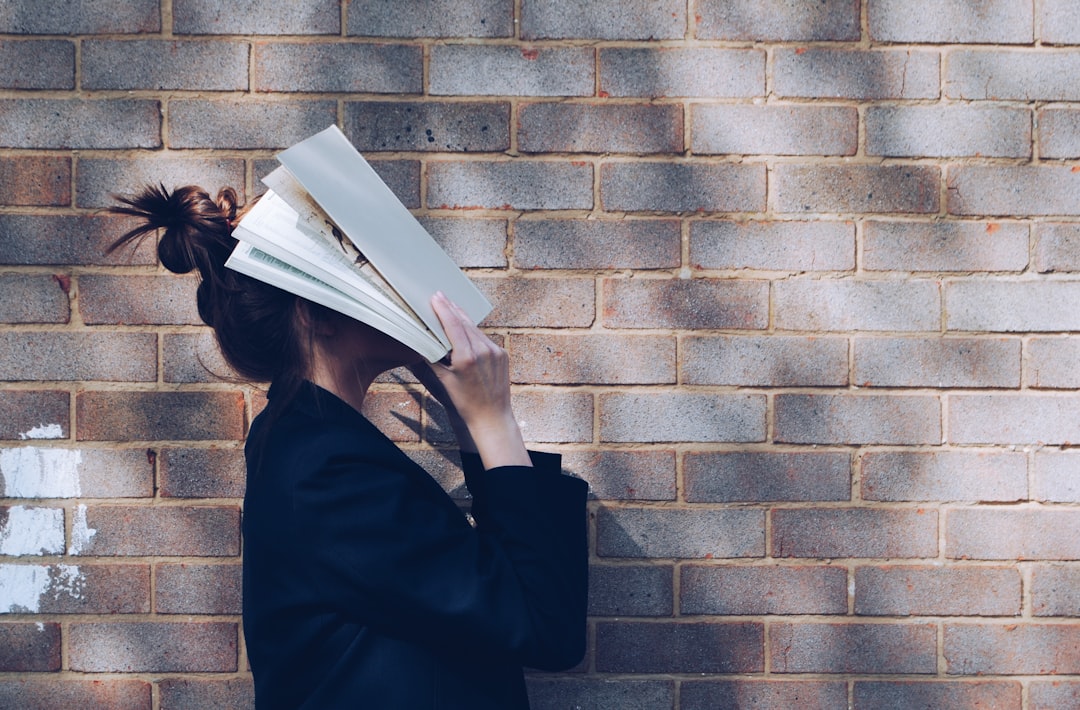名刺はビジネスマンにとっての必須アイテムです。ですが、昨今では大学生でも名刺を持っている人が増えてきています。大学生はどのタイミングで名刺を作るのでしょう。また、就活で名刺は必要なのでしょうか。大学生の名刺のメリットデメリットなども合わせて解説します。
監修者

キャリアアドバイザー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
大学生でも名刺を持つ人はいる
名刺は就職し、社会人になってから持つものと思っていませんか?昨今では、大学生でも名刺を持つ人が増えてきています。ビジネスマンだけの必須アイテムではなくなってきているのです。
名刺にはさまざまなメリットがあります。そのメリットを充分理解した上で上手に活用すると、名刺を持っていない大学生よりも一歩先へ進むことができます。タイミングやメリットデメリット、コツなどについて解説します。
大学生が名刺を作るタイミング
大学生になったからと言って、すぐに名刺を作ってもあまり意味はりません。作りタイミングが大切なのです。それでは、名刺を持っている大学生はどんなタイミングで作っているのでしょう。最もメジャーなタイミングについて解説します。
①所属団体で渉外を任された時
大学生の中には、学生団体のような大きな団体に所属して活動をしている人がいます。例えば、イベントを運営する団体やボランティア活動を積極的に行なう団体などです。
このような所属団体では、外部の人たちとの渉外も必要です。イベントを運営する際には会場を借りるための交渉や、イベントに参加する人たちとコミュニケーションを取らなければならないからです。
そんな時に役に立つのが名刺です。自分がどんな所属団体でどんなポジションを担当しているのかということを名刺で相手に伝えることで距離間が縮まり、渉外もスムーズに進みます。
②学生起業をした時
大学生の中には、学生の間に起業をする人もいます。起業をすれば自分の会社を多くの人たちに知ってもらう必要があります。また、更に会社の規模を大きくするために多くの人たちと関わりあい、協力していくことも大切です。
そのような時に名刺を作っておくと、自分の会社のことはもちろん、自分自身のことも知ってもらえるので大変便利です。名刺交換をしておくと、時間が経った時に縁がつながるということもあります。
学生起業は学生でありながら、社会人としての地位を得たということです。れっきとしたビジネスマンですから、名刺を作る人が多いのです。
③就職活動を始める時
就職活動を始める時に名刺を作る大学生もいます。就職活動時に自分の名刺を渡すなんて早すぎる、と思う人もいるかもしれません。ですが、最近は自分という個性をアピールするために名刺を作り、就職活動時に採用担当者に渡す人が増えてきています。
採用担当者に名刺を渡せば、「自分」という存在を相手に残すことができます。少しでも印象に残して就職へつなげようという積極的な気持ちも、名刺には込められているのです。
大学生が就活時に名刺を作るメリット・デメリット
大学生が就活時に名刺を作ることは、自分の個性を表現するなどのメリットもあります。ですが、実は採用担当者視点でとらえた場合には、デメリットも多いのです。就活中の大学生が名刺を作った場合のメリットデメリットをそれぞれ紹介します。
大学生が就活時に名刺を作るメリット
- 「自分」という存在を採用担当者に残すことができる
- 連絡先の誤りを防ぐことができる
- さまざまな企業の人たちと名刺交換が可能
- その他の就活生とつながることができる
- 後日、お礼を伝えることができる
就活時に増えてきているのが、連絡先の誤りです。最近は電話ではなく、メールでの連絡が主流になっています。
メールアドレスはアルファベットと数字の羅列です。手描き文字は読みにくく、メールが違う人のところに届いてしまうこともあります。名刺にはメールアドレスも記載されていますから、確認することができます。
大学生が就活時に名刺を作るデメリット
- 個人情報が流用される危険性がある
- 無理に背伸びをしているという印象を与える
- 採用担当者が処分に困る
デメリットの中で最も注目すべきは、「処分に困る」です。名刺はその人を表すものであり、その人自身と言っても過言ではありません。そのような大切なものを無下に扱うことは良心の呵責にさいなまれます。
営業などのような会社同士のお付き合いでの名刺なら、後々連絡を取る必要も出てくるので大切に保管します。ですが、就活の場で名刺を受け取ると、連絡を取る可能性が低い場合もあり、処分に困ってしまうのです。
結論|就活時に名刺はいらないが名刺入れは常備する
大学生の就活時に、名刺は不要です。名刺を持っていて交換をしたり配ったりしている人もいますが、それはそのような人が少ないからです。割合が少ないと珍しいため、目立って見えているだけです。
現場での採用担当者の中には、大学生が慣れた手つきで名刺を差し出すと、「痛い人」と思う人もいます。学生の間からすでに名刺を持っている人は、プライドや意識が高いという印象を与えてしまうからです。
プライドや意識が高い人は、会社に入社しても先輩や上司の言うことを聞かず、扱いに困るというイメージが強くあります。採用担当者の中には、そのような人はご遠慮願いたいと思う人もいるため、就活で不利になることもあるのです。
大学生が名刺を作る際のコツ
就活時に大学生が名刺を作るのは、基本的には不要です。ですが、学生団体に所属をしていたり学生起業をしていたりすると、名刺が必要なこともあるでしょう。そのような場合の、イメージが良くなる名刺の作り方のコツをご紹介します。
コツ①|デザインはシンプルに、ロゴは大学ロゴを用いる
デザインはシンプルにしましょう。凝ったデザインの名刺は、「痛い人」という印象を与えてしまいます。あまり良い印象を与えないのです。
また、名刺にはロゴが入っていますが、オリジナルのロゴはあまり良くありません。学生なのですから、大学ロゴを用いるとイメージが良くなります。自分独自のオリジナルロゴは社会人になってからにしましょう。
コツ②|個人情報の記載は必要最小限におさえる
個人情報の記載は必要最小限に抑えましょう。大学生の名刺には、住所や電話番号が記載されていることもあります。ですが、これらは個人情報が流用される可能性があります。
会社の名刺を想像してみてください。記載されているのは、会社の住所や代表電話、そして仕事で使っているメールアドレスなどです。その人本人の個人情報は記載されていません。
大学生が名刺を作る際は、名刺に記載するためのフリーのメールアドレスを取得してそれを記載したり、ホームページやブログなどを解説してそのアドレスを記載したりしましょう。
コツ③|裏面には英語で情報を記載する
大学生の名刺は会社の名刺と違って、記載する情報があまり多くありません。ほとんどの場合は、表面だけで伝えたい情報の記載が終わってしまうでしょう。ですが、裏面が真っ白なのは格好悪いと思う人もいるかもしれません。
そんな時は、裏面には英語で情報を記載しましょう。大学生ですから、もしかしたら海外の学生と交流することもあるかもしれません。裏面に英語で情報を記載しておけば、そのような場面でも名刺が大活躍してくれます。
大学生でも簡単に名刺を作れる4つのサイト
名刺を作ることができるサイトはネット上でたくさん公開されています。ですが、たくさんの数がありすぎて、どのサイトがいいのかわからないという人もいるでしょう。そこで、大学生でも簡単に作れる名刺サイトを4つ、ピックアップしてご紹介します。
①Canva
このサイトは、料金プランが3つ設定されています。無料プランでも、名刺のデザインは8000種類以上から選択することができるので、とても便利です。学生や就活用のデザインも用意されているのが人気の秘訣です。
印刷は、自宅のプリンターを利用するか印刷業者に依頼します。自宅で印刷できる環境なら、すぐに名刺を作ることができます。
②vistaprint
シンプルなデザインから、個性的なデザインまで様々な種類が揃っています。同じデザインの中にも色違いがあるので、自分だけの名刺を作ることが簡単です。
文字やデザインを目立たせるような特殊加工をすることもできます。他の人とは違うオリジナリティな名刺を作りたい人におススメです。
③デザイン名刺.net
シンプルなものからゴージャスなものまで、幅広いデザインが用意されています。学生や就活用の人のためのシンプルでありながら、個性的なデザインも取り扱っているので、大学生で初めて名刺を作る人にも安心です。
④ラクスル
多くの名刺作成サイトの中で、最も低価格で作成できるサイトです。とにかく安く名刺を作りたいという人におススメです。
デザインもシンプルなものが揃っています。学生や就活用の名刺として活用できるシンプルなものが多いので、派手な名刺を作りたくない人にもおススメです。
まとめ
自分の名刺を作っている大学生をよく見かけます。ですが、絶対数ではまだまだ少ないというのが現状です。もし、大学生の間に名刺を作りたいと思うのなら、個人情報やデザインには注意しましょう。