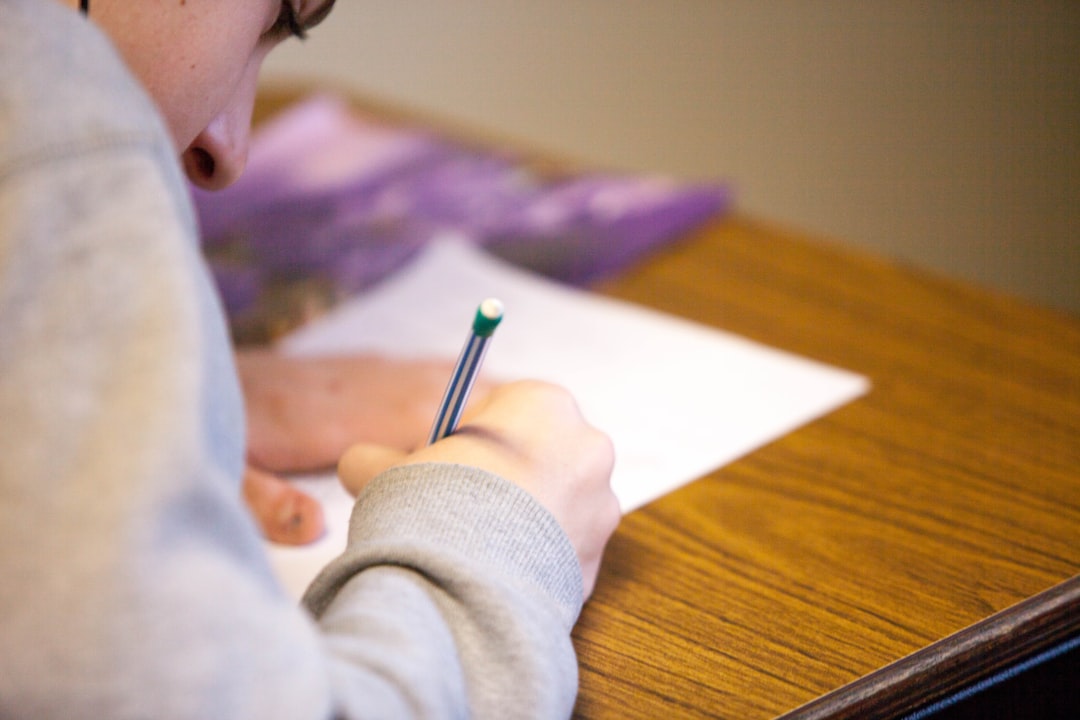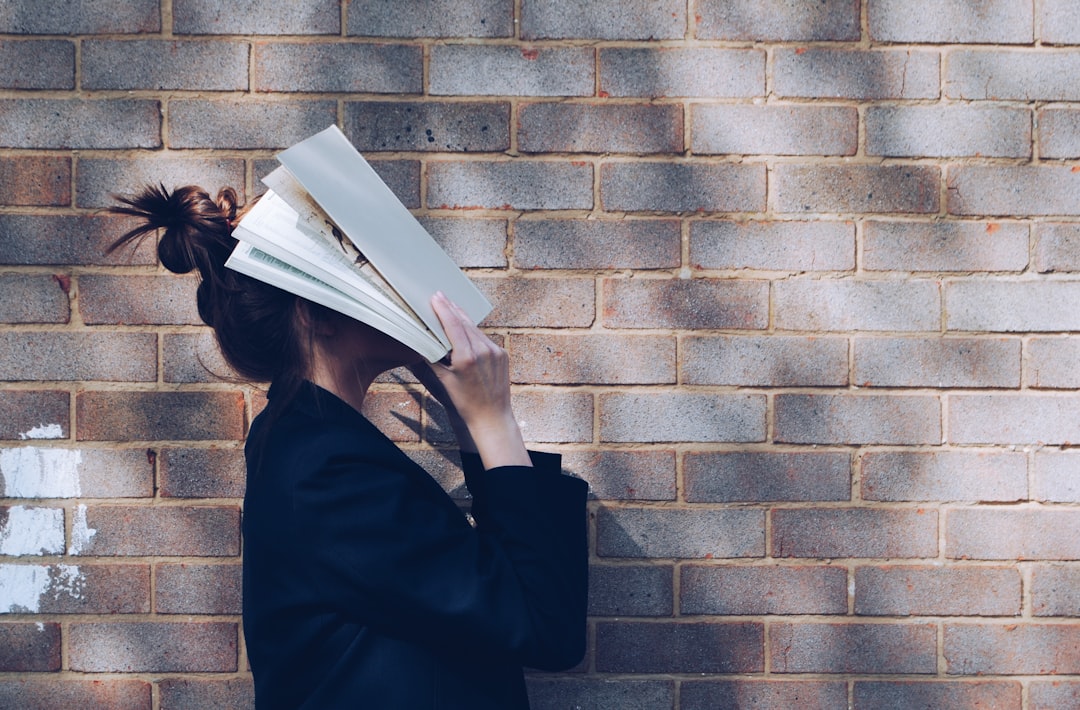先が見えない世の中だからこそ、安定した仕事に就きたいという思いから、公務員試験の受験準備をしている人も多いことでしょう。その場合、合格を目指すなら倍率を知っておくことは大事です。そこで今回は、公務員試験の種類や試験内容、倍率の違いなどについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。
監修者

キャリアアドバイザー|秋田 拓也
厚生労働省のキャリア形成事業にキャリアコンサルタントとして参画。
大手警備会社にて人事採用担当として7年間従事の後、現職にて延べ200名以上の企業内労働者へキャリアコンサルティングを実施。
■所持資格
国家資格キャリアコンサルタント、産業カウンセラー、CDA(キャリア・デベロップメント・アドバイザー)
公務員試験の倍率はどれくらい
公務員と一口にいっても、「国家公務員」と「地方公務員」があり、そこからさらに職種に分かれるため、様々な試験が行われています。そのため、自治体や職種によって、公務員試験の倍率が変わります。試験内容も異なるため、公務員の中でもどの職種を選ぶのかを検討し、試験に備える必要があります。
公務員試験の倍率
国家公務員と地方公務員、専門職か否かなど、公務員試験の倍率は試験内容によって異なります。最も高いもので138.4倍、低いと2倍以下になる例もあるようで、平均は5~6倍といわれています。ここでは、国家公務員と地方公務員の倍率について説明します。
国家公務員の倍率
ここでは「公務員試験総合ガイド」で公開されている情報に基づき、2019年の国家公務員試験倍率を表にまとめてみました。
国家公務員の倍率で一番高いものが138.4倍、低いものは2.8倍と大きな開きがあることがわかります。
地方公務員の倍率
前章同様に、「公務員試験総合ガイド」で公開されている情報に基づき、2019年の地方公務員試験倍率を表にまとめてみました。
地方公務員でも一番高い倍率が31.7倍、低いものは2.5倍と大きな開きがあることがわかります。また、政令指定都市・東京特別区の公務員試験の倍率も、前述した資料を参考として以下にまとめておきます。
いわゆる市役所職員・区役所職員として採用される公務員ですが、国家公務員より倍率が高いものも少なくありません。
公務員試験の内容
公務員試験は自治体や職種によって試験内容が変わるものの、「筆記試験」と「面接試験」に大別されることは共通しています。筆記試験である程度まで人数を絞り込んだうえで、面接試験が行われます。ここでは、公務員試験の内容について詳しく説明します。
筆記試験
公務員試験における筆記試験には論述試験が含まれており、「教養」と「専門」に分かれます。ここでは、それぞれの科目の特徴を詳述します。
教養科目
筆記試験における教養科目とは、正式には「教養論文試験」といいます。社会や経済など一般的な課題をテーマとして与えられ、自分の考えを論述します。時間は60~80分程度で、800~1,200文字の小論文を書くことになります。
テーマを理解し、その客観的な事実をベースに自分の考えを論理的に文章化することが求められます。これは、どの職種であっても課されます。
専門科目
筆記試験における専門科目とはあ、正式に刃「専門記述試験」といいます。国家総合職をはじめ、外務専門職、東京都Ⅰ類B(一般方式)、裁判所一般職、国税専門官、財務専門官など、一部の公務員試験で採用されています。
上記の専門職として必要な専門科目に関するテーマを与えられ、小論文を書くこととなります。
面接試験
筆記試験をクリアすると、面接に進むことになります。公務員試験で行われる面接には、以下のものがあります。
- 個別面接/2次試験以降で必ず実施。受験者1名に対し、面接官が3~5名つく。時間は15~30分程度
- 集団面接/受験者は3~8名、面接官が3~4名が一般的。質問に対する回答は、面接官からの指名もしくは受験者の挙手による
- 集団討論/受験者を5~10名集め、与えられたテーマに基づいてグループ討議を行う
面接試験の回数や内容は、受ける自治体によって異なります。
大卒・高卒でどのくらい違いがあるか
公務員試験は、学歴によって受けられる種類が変わります。それを踏まえて、自分がどの公務員試験を受験するのかを決めなければなりません。ここでは、公務員試験が大卒・高卒でどのくらい違いがあるかについて説明します。
高卒で受けられる公務員試験
高卒で受けられる公務員試験には、以下のものがあります。
- 国家公務員一般職(高卒程度試験)/各省庁の初級係員として実務を担当する
- 裁判所事務官Ⅲ種/裁判所書記官のもとで民事事件や刑事事件に関わる事務作業を行う、または裁判所の総務や会計などの業務を担う
- 地方公務員初級/警察官や消防官、水道局局員、正同局局員など、地域住民の日常生活をサポートする業務を担う
高卒であっても、国家公務員・地方公務員の両方を目指すことができます。
大卒・高卒から見た倍率
公務員試験を受けるにあたり、大卒と高卒では倍率にどのような違いがあるのか、気になる人も多いことでしょう。ここでは各種サイトの情報をもとに、2018年の国家公務員一般職試験を例にあげ、大卒・高卒から見た倍率を比較してみます。
上記は大卒は行政職、高卒は事務職の最終倍率を比較しています。地方によって大卒・高卒の最終倍率の高低には違いがありますが、合計値では大卒がやや上回っています。ただし、高卒者の2倍以上の大卒者が公務員試験を受けていることを考えると、難易度は高いといえるかもしれません。
公務員試験の難易度
公務員試験と一口にいっても、資格名称が多岐にわたり、難易度も異なります。ここでは、各種サイトの情報に基づき、公務員試験の難易度について説明します。
国家公務員試験の難易度
国家公務員試験の中でも、難易度が高いといわれる試験を上から10種類、抜粋してみました。
- 国家公務員総合職(財務省・警察庁)
- 国家公務員総合職(経済産業省・総務省・外務省)
- 国家公務員総合職(人事院・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・環境省・防衛省)
- 衆議院事務局職員(総合職)
- 参議院事務局職員(総合職)
- 衆議院事務局職員(総合職)
- 参議院事務局職員(総合職)
- 裁判所事務官
- 国立国会図書館職員一般職(大卒)
- 国立国会図書館職員総合職
総じて、国家公務員総合職の難易度が高いことがわかります。希望する省庁によって、難易度に多少違いはあります。
地方公務員試験の難易度
同様に、地方公務員の中でも難易度が高いものは、以下の通りです。
- 都道府県庁職員
- 特別区職員
- 政令都市職員
警察や消防、教員などの採用試験は、上記に比べると難易度が低いようです。
受かりやすい公務員試験はどこか
公務員になりたいという気持ちはあっても、難易度が高いところを受ける自信がないという学生も多いものです。確実に公務員になることを目指すなら、受かりやすい職種を目指すのも選択肢の一つです。ここでは、比較的に受かりやすいといわれている公務員試験を3つ、紹介します。
①国税専門官
1つめは、国税専門官です。公務員試験全般にいえることですが、受験者が複数の試験を受けていることを想定し、採用予定人数を大幅に上回る人数を合格させています。中でも国税専門官は、採用予定者の3倍弱の合格者を出していることで知られています。
また、他の公務員試験と受験日が重なりにくいので、候補の一つとして受験しておくことをおすすめします。
②国家公務員(一般職)
2つめは、国家公務員(一般職)です。公務員は定年の60歳を迎えても、再任用期間として65歳まで働くことができます。しかしそれを満了する人が増えており、職員不足であるため、国家公務員(一般職)の採用人数を増やしています。
国家公務員(総合職)より試験の難易度も低いので、チャレンジしてみるとよいでしょう。
③地方自治体(都道府県庁)
3つめは、地方自治体(都道府県庁)です。就活生の民間企業志向が高まることで、ここ数年は公務員の人気が低下していました。地方自治体(都道府県庁)はその影響を大きく受けており、内定辞退者も少なくありません。
そのため、地方自治体(都道府県庁)の合格率は二桁に届くところが多く、国家公務員より受かりやすくなっています。
今後の公務員試験の動向
2020年に入り、コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の発令など、就活生には予測がつかない状況が続いています。そしてその影響は、ついに公務員試験にも及びました。ここでは、今後の公務員試験の動向について説明します。
試験は延期される
2020年4月8日に人事院は、2020年度の国家公務員総合職試験の延期を発表しました。2020年4月26日に予定されていた一次試験が、5月24日に延期されています。コロナの感染収束が実現しない今、こうした判断が地方で起こる可能性もあります。公務員試験のスケジュールについては、こまめに確認することをおすすめします。
まとめ
今回は、公務員試験の種類や試験内容、倍率の違いなどについて解説しました。
コロナウイルス感染拡大に伴い、民間企業の業績悪化が予想される今、公務員試験への挑戦を検討する就活生も増えています。試験の難易度や仕事内容に関するリサーチをしっかり行い、公務員受験合格ができるよう、しっかり準備しましょう。